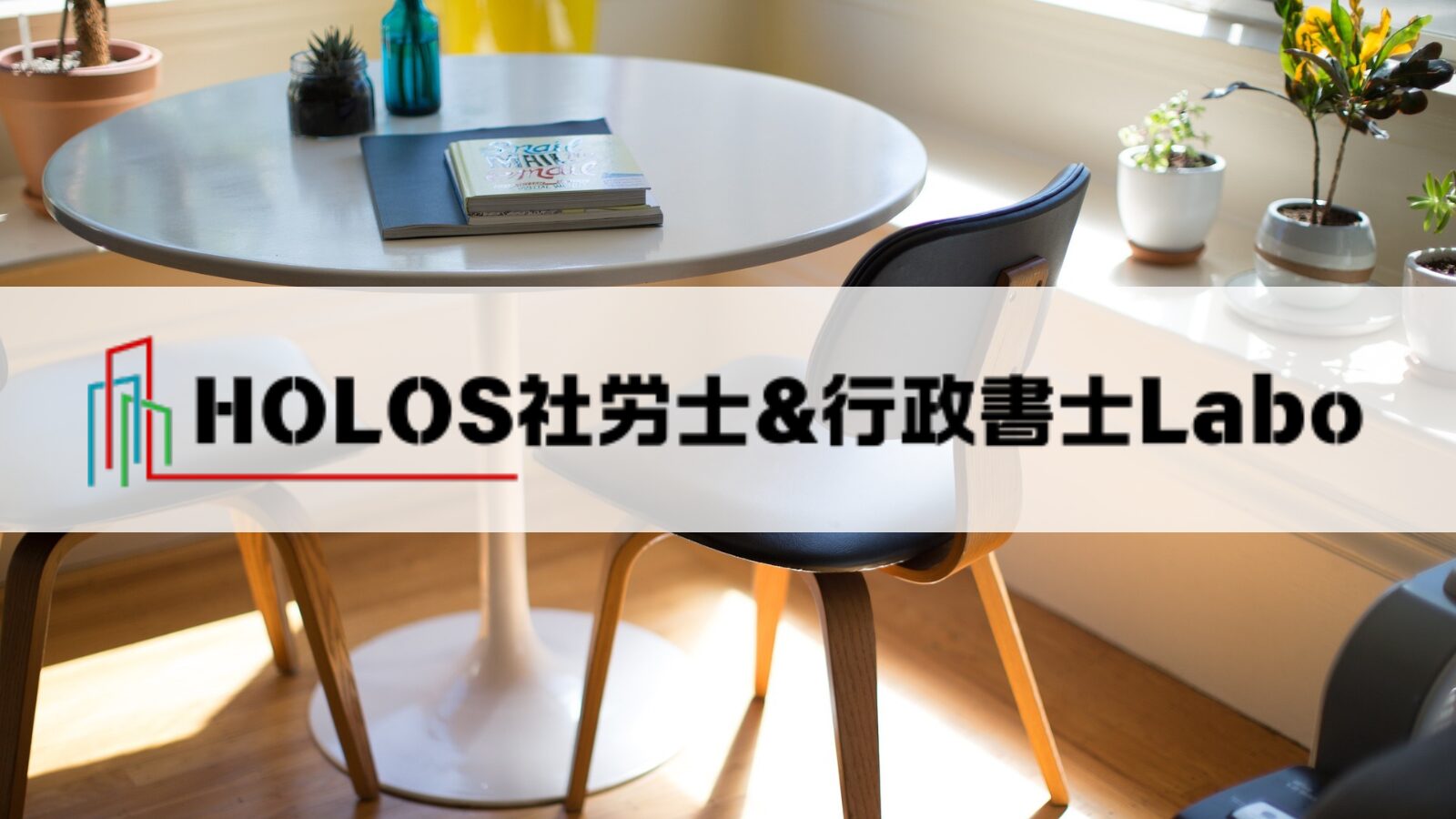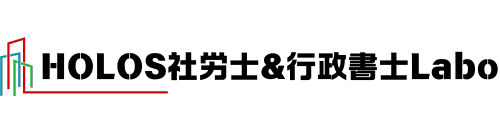「182円が8690円に?」OTC類似薬の保険見直しで変わる医療と暮らし
こんにちは。医療・薬局・介護の現場支援に携わっている立場から、今回は2026年度から段階的に始まる「OTC類似薬の保険適用見直し」について解説します。
OTC類似薬とは?
「OTC類似薬」とは、市販薬(OTC医薬品)と同じ有効成分・効能を持つ処方薬のことです。風邪薬、湿布、目薬、花粉症薬などがその代表です。
現在は処方箋を通して保険適用で手に入りますが、これを市販薬に“置き換えられる”として、国は医療費抑制の一環として保険適用の見直しを検討しています。
2026年度から段階的に適用除外へ
政府は「骨太の方針2025」で、2026年度からOTC類似薬の保険適用を段階的に見直す方針を明記しました。
これにより──
- 現在、30日分で182円程度だった薬が、保険が効かなくなると8690円に
- 複数の市販薬を使わざるを得なくなった場合、月数万円単位の薬代負担が発生する可能性もあります
とくに、アレルギー・皮膚疾患・腰痛など、慢性的な軽症疾患を抱える方にとっては深刻な影響が出ることが予想されます。
利用者が今できる備えは?
薬剤師の立場としては、以下の備えをおすすめします:
- まずは自分の薬が対象になるかを確認
かかりつけの医師や薬剤師に「この薬は将来、保険が外れる可能性があるか?」を早めに相談してみましょう。 - 代替市販薬の価格・効果を把握しておく
薬局などでOTC医薬品の選択肢や価格差を比較しておけば、いざというときに慌てず対応できます。 - セルフメディケーション税制の活用を検討
市販薬の年間購入額が一定を超えた場合、医療費控除の対象となる制度です。
現場への影響と制度の“正しい理解”
この見直しは「無駄な医療費削減」の観点で語られがちですが、医療機関や薬局の現場では以下のような懸念もあります:
- 保険が使えないことで受診控えや服薬中断が起き、重症化を招くリスク
- 説明不足による患者との信頼関係の揺らぎ
- 処方外しの対応に追われる現場スタッフの負担増
患者負担が増える中で、医師や薬剤師が「なぜこの薬が保険外なのか」を丁寧に説明できる体制が求められます。
制度と労務管理の視点
このような制度変更があると、医療・薬局・介護の現場では:
- スタッフへの説明教育の徹底
- 業務フローや接遇マニュアルの更新
- 苦情・問い合わせ対応の整備
が必要となり、労務管理・職場体制づくりにも影響します。これらは処遇改善や評価体制の強化にもつながる分野であり、制度の正しい理解と社内浸透が重要です。
HOLOSができること
HOLOS(ホロス)社労士&行政書士Laboでは、制度変更に伴う影響分析からスタッフ教育の設計、制度活用の支援(ベースアップ評価料や体制整備)まで、医療・介護・薬局の皆さまをサポートしています。
薬局やクリニックで「患者さんにどう説明すればいいのか」「職員にどう伝えればいいのか」とお悩みの方は、ぜひご相談ください。
患者の安心を守るためには、「薬が出るか出ないか」ではなく、「なぜそうなるのかを伝えられる体制」が不可欠です。
制度を敵にせず、味方につける視点。
HOLOSはその“つなぎ役”として、現場の皆さんとともに歩んでいきます。
投稿者プロフィール