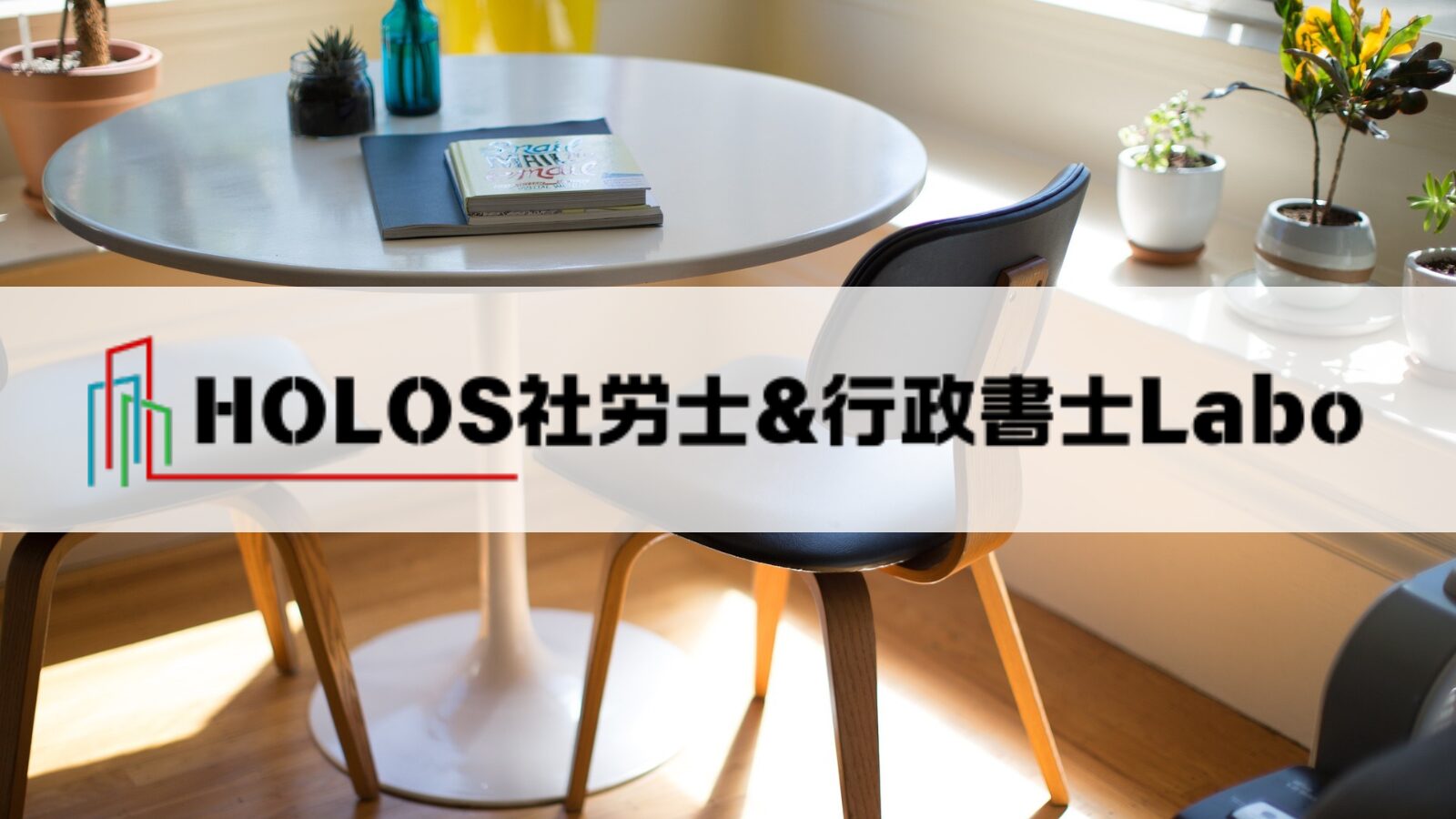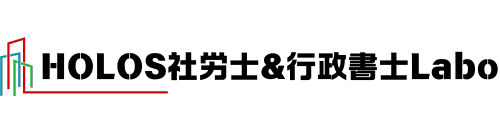【リベンジ退職という“静かな警鐘”】職場に潜む構造的ミスマッチとどう向き合うか
「リベンジ退職」という言葉をご存じでしょうか?
退職時に引き継ぎを拒否したり、社内情報をSNSに晒したりするなど、“意図的に企業へダメージを与える”辞め方です。
静かに辞める「静かな退職(Quiet Quitting)」とは異なり、これは明確な“怒り”と“報復心”に根ざした行動であり、実際にこうした退職が増えていると言われています。
一見、感情的な行動に思えますが、背後には組織と個人の信頼関係の崩壊、労働環境と人間関係の深刻なミスマッチがあるケースがほとんどです。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/f2cfcf0f3b31fdd3d1a39c1f9fff0ee7c8c5aedf
■なぜリベンジ退職が起きるのか?その背景とは
- 入社前後での労働条件や期待値のギャップ
- 上司とのコミュニケーションの欠如
- 成長機会の不在とキャリア形成の不透明さ
- 結果ばかりを重視し、プロセスや努力が評価されない仕組み
- 心理的安全性の欠如(ものが言えない空気、対話のなさ)
こうした要素が複雑に絡み合い、働く人に「裏切られた」という感覚を残すと、それが爆発的な形で“最後の一撃”に転化されてしまいます。
■医療・薬局・介護業界でも無関係ではない
医療機関や介護事業所、薬局といった現場は、「対人援助職」として高度な感情労働を求められます。
患者・利用者・家族への対応だけでなく、内部での協力関係、チーム連携、そして業務負担――。
このような職場で、「評価されていない」「理解されていない」と感じたとき、
その失望の深さは非常に大きく、静かな退職を飛び越えて“攻撃的な離職”につながることもあり得るのです。
■制度は「ある」だけでは足りない ―運用と説明の“熱量”が問われる
医療機関には「ベースアップ評価料」、介護事業所には「処遇改善加算」という国の支援制度があります。
いずれも、職員の賃金改善や職場環境向上を後押しする仕組みです。
これらの制度では、賃金規程の改定や職員への周知が義務付けられており、「配分の透明性」は制度的に担保されています。
ただし、実際の運用では「説明が一方的だった」「昇給額が期待に届かない」など、“納得感”の課題が残ることも事実です。
制度を整えるだけでなく、対話による合意形成・評価へのフィードバック・上司の説明責任といった、運用上の“熱量”が職員の信頼形成には不可欠です。
■薬剤師・社労士として現場で感じること
薬剤師として、また社労士として、私は次のような実例に数多く触れてきました:
- 「制度はあるのに、現場では誰も内容を理解していない」
- 「評価の基準がなく、何をすれば昇給するか分からない」
- 「上司と話す機会すらなく、職場が“点”でバラバラになっている」
これでは、せっかくの制度が空回りし、むしろ逆効果になる可能性すらあります。
職場の制度や評価の“透明度”が低いままだと、退職は静かでは済まない――。
それがリベンジ退職の本質的な教訓ではないでしょうか。
■企業側が今、取り組むべきこと
- 1on1面談や定期フィードバックによる対話の習慣化
- 結果とともに“努力やプロセス”も評価できる制度の整備
- 期待と現実のギャップを埋める入職後のフォローアップ
- 管理職研修(心理的安全性、感情の扱い方、傾聴技術)
制度ではなく「日常のやり取り」「現場の文化」こそが、信頼を支える本体なのです。
■まとめ:リベンジ退職は、“組織の状態を映す鏡”
退職者を一方的に“裏切り者”と見るのではなく、
「その人が辞めざるを得なかった理由」を探る姿勢が、組織を健全にする第一歩です。
医療・介護・薬局――どの業界でも、処遇改善は制度だけに頼る時代ではありません。
HOLOS社労士&行政書士Laboでは、宮城県・仙台を中心に、
制度整備 × 実効的運用 × 感情に配慮した職場設計を支援しています。
📩 ご相談・お問い合わせは、https://holos-labo.com/contact/ のお問い合わせフォームからどうぞ。
HOLOS社労士&行政書士Labo
投稿者プロフィール