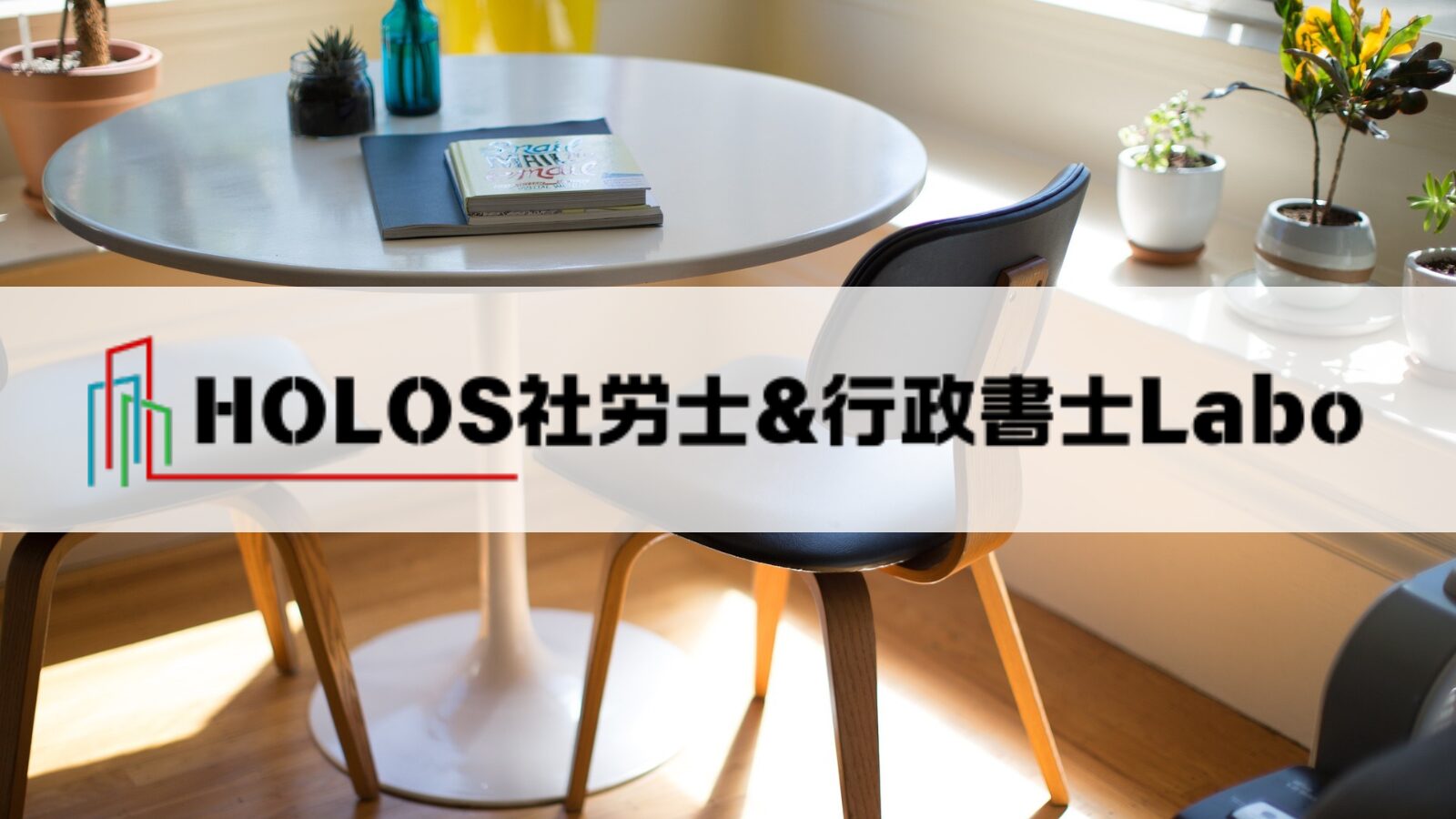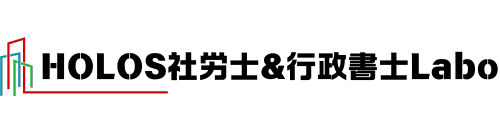【再検証へ】医療ひっ迫で“入院できず死亡”──高齢者施設を襲った現実とこれから求められる備え
新型コロナウイルスの第4波、全国で入院できず施設内で亡くなる高齢者が相次いだ現実をご存じでしょうか?
当時は「原則入院」と位置づけられていたにもかかわらず、病床ひっ迫により**“みとり”を余儀なくされた現場が存在しました。
この実態を明らかにしようと、鹿児島大学・佛教大学の研究グループが全国600以上の高齢者施設を対象とした調査**を開始します。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250508/k10014799101000.html
■入院できなかった現実──医療機関・施設・保健所の「限界」
兵庫県西宮市の特別養護老人ホーム「甲寿園」では、
感染対策を徹底していたにもかかわらずクラスターが4回発生。
2021年春の【第4波】では20人の感染者中、6人が重症化。
しかし病床はひっ迫し、保健所からは「入院先が見つからない」という回答。
結果として、施設の看護師や嘱託医が酸素投与や吸引を行いながら、施設内での“みとり”を選ばざるを得なかったのです。
施設職員の記録には当時のやり取りが残されています:
「同じ状況の人がたくさんいてベッドが空かず難しい」
「クラスターが起きた時は、みとりをしてもらう」
一方、西宮市保健所は限られた病床確保のため、県外への入院調整を行うも【1日40人以上が入院待機】。
【第4波の病床使用率は最大85.1%】に達し、
“原則入院”は現場感覚として既に機能していなかったことが浮び上がります。
■「医療アクセスを守る」ためにできること
施設側は、感染対策に加え、
- ゾーニング強化
- 職員配置の見直し
- 看取り体制の整備
など即応的な対応を行いましたが、
こういった事態を踏まえると、今後は制度的な備えと職場環境づくりが欠かせません。
具体的には、
✅ BCP(業務継続計画)の策定・見直し
✅ 処遇改善加算やベースアップ評価料活用による人員確保や処遇改善
✅ 多職種での感染症対策研修や協力医療機関との連携強化
特に、宮城県・仙台市の医療機関や介護施設でも、
「病床ひっ迫時の支援体制整備」や「地域医療との連携強化」が求められています。
■HOLOS社労士&行政書士Laboができる支援
パンデミック下で浮き彫りになったのは、制度上の整備だけでなく、職場ごとの緊急時対応体制の差でした。
私たちは、薬剤師×社労士のハイブリッド視点から、次のような具体的支援を行います。
✅1.医療・福祉施設向け【緊急時労務対応マニュアル】の作成
- 自施設でクラスターが発生した場合の人員配置再編ルール
- 隔離対象者への勤務免除・有給対応・給与計算モデル
- 家族連絡・看取りへの備えと従業員の心理的ケア方針
✅2.「入院できないリスク」に備えた【業務継続計画(BCP)】の構築支援
- 医師不在時に対応できる看護・介護職の役割設計
- 医療物資不足時の調達ルール、代替手順
- 自治体との医療連携・入院調整のプロセスマップ作成
✅3.【加算制度活用】による人員確保と処遇安定支援
- 処遇改善加算・ベースアップ評価料の実務的な届出支援
- 「コロナ対応を担った職員への特別手当制度」の設計
- 慢性的な人手不足を見据えた非常勤・夜勤職員の確保戦略
✅4.施設×薬局の連携強化コンサルティング
- 嘱託医・訪問薬剤師との緊急対応フロー整備
- 抗感染症薬の在庫と搬送ルート・管理体制の見直し
- ワクチン接種時の説明・体制支援
✅5.感染症発生後の【監査対応・記録整備支援】
- 都道府県からの指導・監査対応に備えた記録テンプレート提供
- ゾーニング・感染対策の写真・文書保存サポート
- 入所者家族との記録的対応方針の整備
これらを通じて、**再発を防ぎながらも、起きたときに「慌てず対処できる施設体制」**を一緒に構築していきます。
施設職員の皆さんが“見ているだけしかできなかった”という苦しい状況に、二度と直面させないために。
HOLOS社労士&行政書士Labo
薬剤師・社労士・行政書士
石田 宗貴
投稿者プロフィール