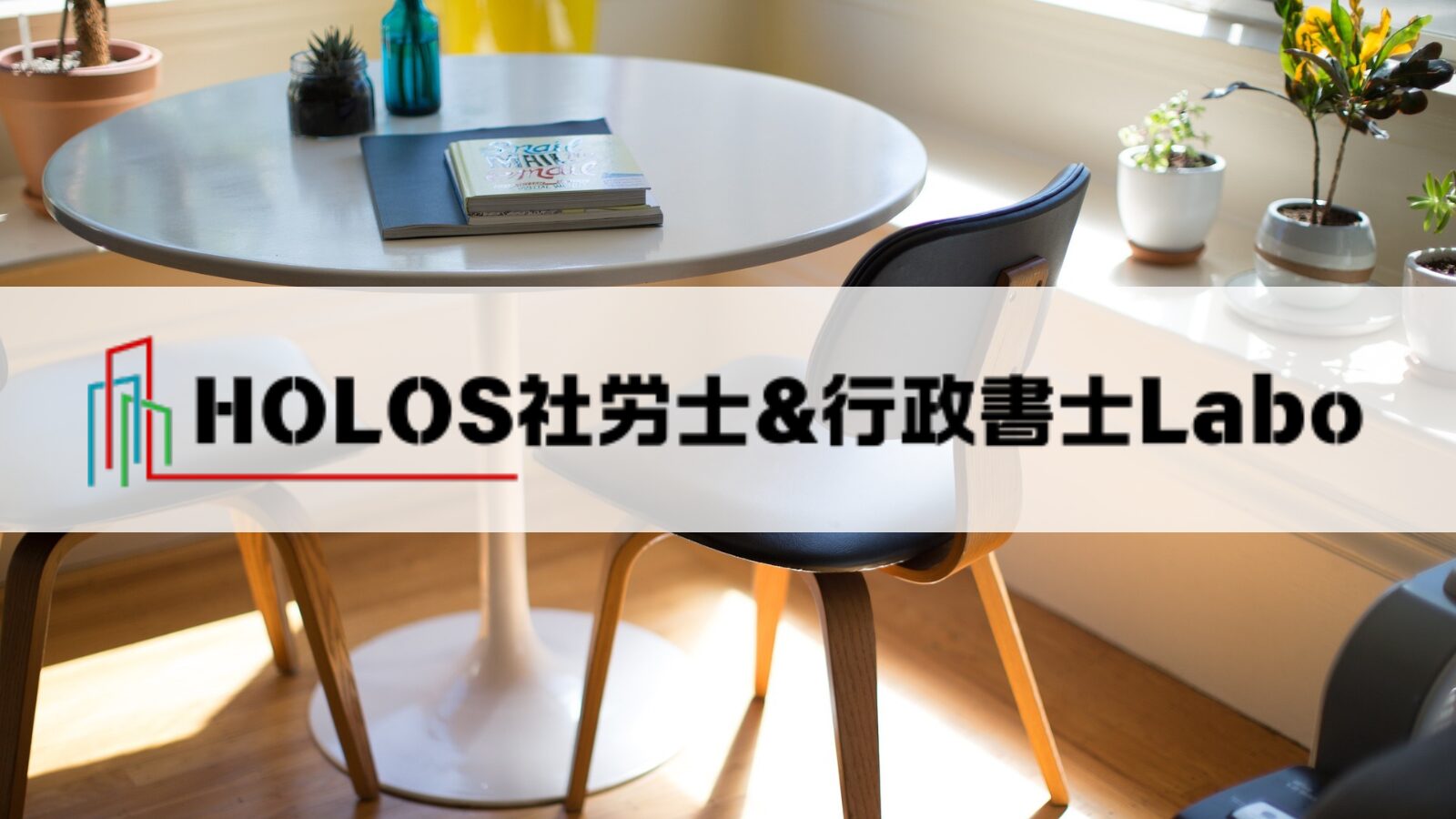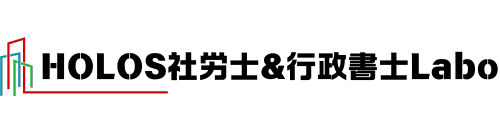【合理的配慮義務化】デジタル化の陰で困る視覚障害者たち ~セルフレジ問題と私たちにできること~
視覚障害者、タッチパネルに困惑=広がるセルフレジ、障壁多く―当事者団体「環境整備も進めて」|最新医療ニュース|時事メディカル|時事通信の医療ニュースサイト
2023年4月施行の改正障害者差別解消法により、企業や事業者には「合理的配慮」の提供が義務化されました。しかし、「環境整備」については努力義務に留まっており、現場では十分に対応できていないケースも目立っています。
特に問題となっているのが、店舗で急速に普及するセルフレジ。視覚障害者にとって、タッチパネルの操作は大きな壁です。モデルの宇佐亮さん(23歳、横浜市在住)も、行きつけのドーナツ店でセルフレジに戸惑った経験を語っています。点字表記や読み上げ機能がなく、周囲に助けを求めざるを得ない状況が続いています。
日本視覚障害者団体連合によると、行政や事業者のデジタル化に対し、68.4%の視覚障害者が「困っている」と回答。セルフレジに加え、インターネットバンキングやワンタイムパスワードによるログイン認証でも不便さを感じる声が上がっています。
視覚障害を持つ同連合の情報部長・吉泉豊晴さん(67歳)は、「デジタル化の波に私たちは取り残されている」と警鐘を鳴らし、「無人店舗の拡大に伴い、合理的配慮を受けられないリスクが高まっている」と訴えています。
■薬剤師・社労士としての視点 ~すべての人にやさしい社会を~
薬剤師の皆さまにとっては、セルフレジ対応が進むドラッグストアや調剤薬局の現場でも、視覚障害者への配慮が不可欠です。たとえば、読み上げ機能付きセルフレジの導入、有人レジの併設、案内担当者の配置など、患者ファーストの環境整備が求められます。
社労士の立場では、企業に対して障害者差別解消法に基づく合理的配慮義務への対応状況を確認し、就業環境や顧客対応方針の整備支援を行うことが重要です。また、障害者雇用促進法に基づき、デジタル機器のアクセシビリティ確保も助言すべきポイントでしょう。
デジタル化の加速する今こそ、誰一人取り残さない社会の実現に向け、私たちができる行動を見直していきましょう。
投稿者プロフィール