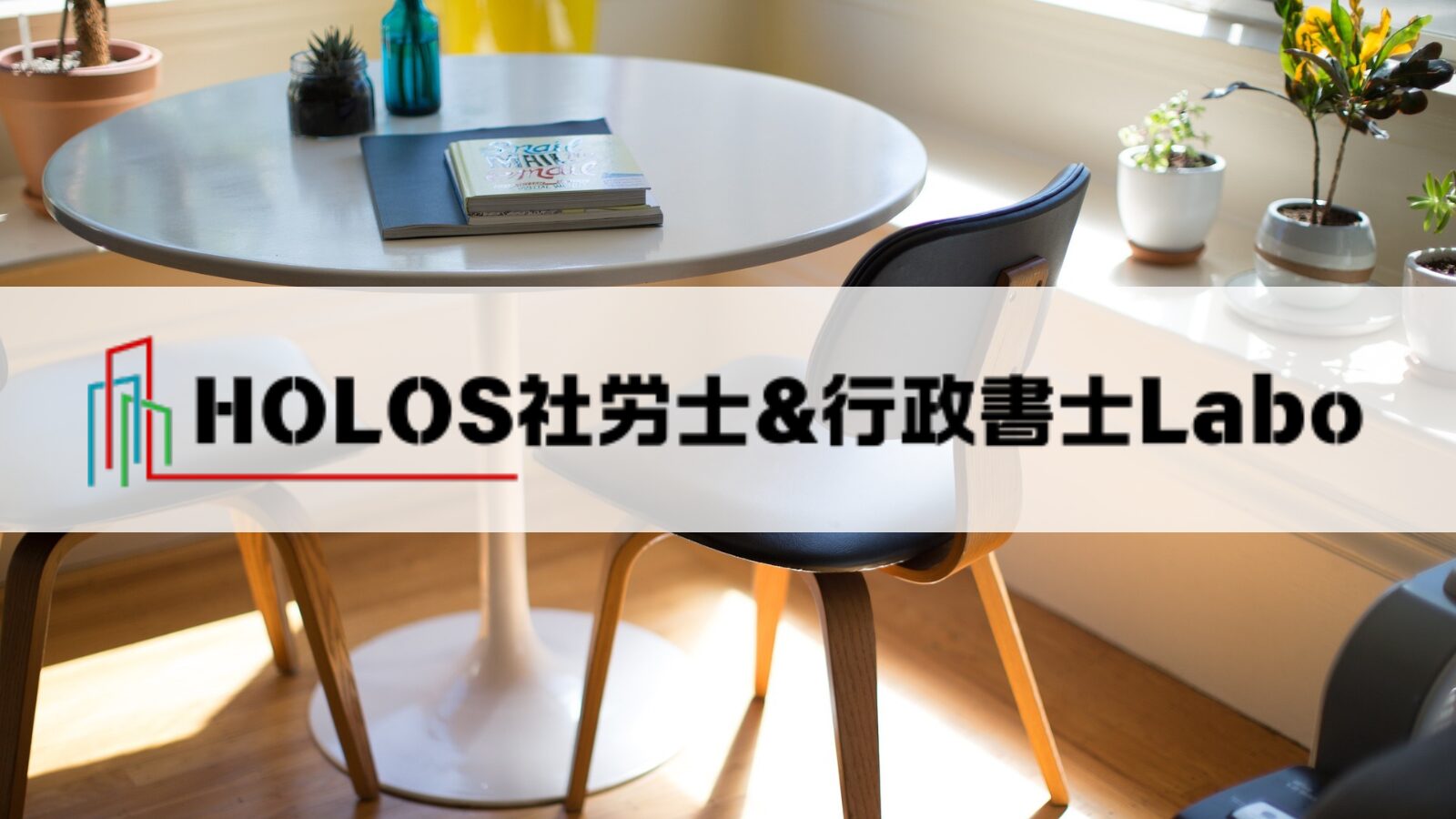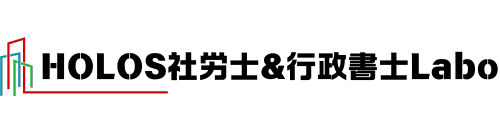【腹膜透析の再評価】高齢社会に求められる“自宅でできる医療”とは?
日本には、慢性腎臓病の患者が約1500万人。
そのうち透析治療を受けている方は、2023年末時点で約34万人にのぼります。
しかし、そのうち腹膜透析を受けている人は、わずか3%程度。
いま、この“在宅でできる透析”が高齢化の中で再評価されています。
https://www.asahi.com/sp/articles/AST4X2RRWT4XUTFL00BM.html?iref=sp_apital_medicalnews_list_n
■「腹膜透析」と「血液透析」の違いとは?
透析には大きく2つの種類があります。
血液透析(HD):週3回程度、医療機関に通い、ダイアライザーという機械を使って血液をきれいにします。1回あたり約4時間。
腹膜透析(PD):自宅で1日3回程度、腹腔内に透析液を出し入れし、自身の腹膜を“フィルター”代わりに使って老廃物を除去します。1回30分程度、夜間にまとめて行う方法もあります。
腹膜透析は自宅で実施可能であり、体への負担が少ないという特徴があります。
■なぜ“たった3%”しか選ばれていないのか?
背景にはいくつかの要因があります。
血液透析が先に普及し、医療機関の設備や人材も血液透析に集中 腹膜透析は患者ごとの調整が多く、“テーラーメイド医療”で手間がかかる 医師や看護師の教育が追いついていない 医療機関が収益的に腹膜透析を積極導入しづらい構造
特に地方の医療機関やクリニックでは、在宅透析支援の仕組みが整っていないケースも多くあります。
■高齢化とともに「選ばれる理由」が増えている
透析導入の平均年齢は、1983年の52歳から現在は72歳に上昇。
原因疾患も、糖尿病から加齢に伴う腎硬化症が増加しています。
血液透析では、血圧低下・疲労感・認知機能低下リスクなど、高齢者には負担が大きい側面があります。
一方で腹膜透析は…
徐々に老廃物を除去するので身体的負荷が少ない 水分・食事制限が比較的緩やか 90代でも導入可能 夜間自動交換装置で生活に合わせた選択も可能
といった柔軟性があり、今後の在宅医療・地域包括ケアとの親和性も高いとされています。
■薬剤師×社労士としての視点:必要なのは制度と現場の“橋渡し”
私は薬剤師と社労士の資格を持ち、医療・薬局・介護に関わる現場支援をしていますが、
腹膜透析の普及には**「制度はあるけど現場が対応できない」問題**が根強く残っていると感じます。
たとえば…
薬局での透析関連物品の支援体制
在宅医療を担う人材(訪問看護・医師・薬剤師)との連携設計
地域医療連携や自治体とのスムーズな情報共有と研修体制
これらがないと、腹膜透析は選択肢にすらなり得ません。
■HOLOSとしてできること
仙台・宮城県を中心に活動するHOLOS社労士&行政書士Laboでは、
次のような支援を通じて、「在宅で可能な医療」の普及を後押ししています。
・透析対応医療機関の体制整備コンサル
・在宅医療を担う医療機関の人事・労務支援
・医療・薬局・介護の連携体制づくり
・ベースアップ評価料・処遇改善加算など制度活用支援
「選ばれない」のではなく、「選べない」現場に、選択肢を増やすこと。
それが、地域医療の次のステージだと考えています。
▶ ご相談・お問い合わせは https://holos-labo.com/contact/よりお気軽にどうぞ。
HOLOS社労士&行政書士Labo
投稿者プロフィール