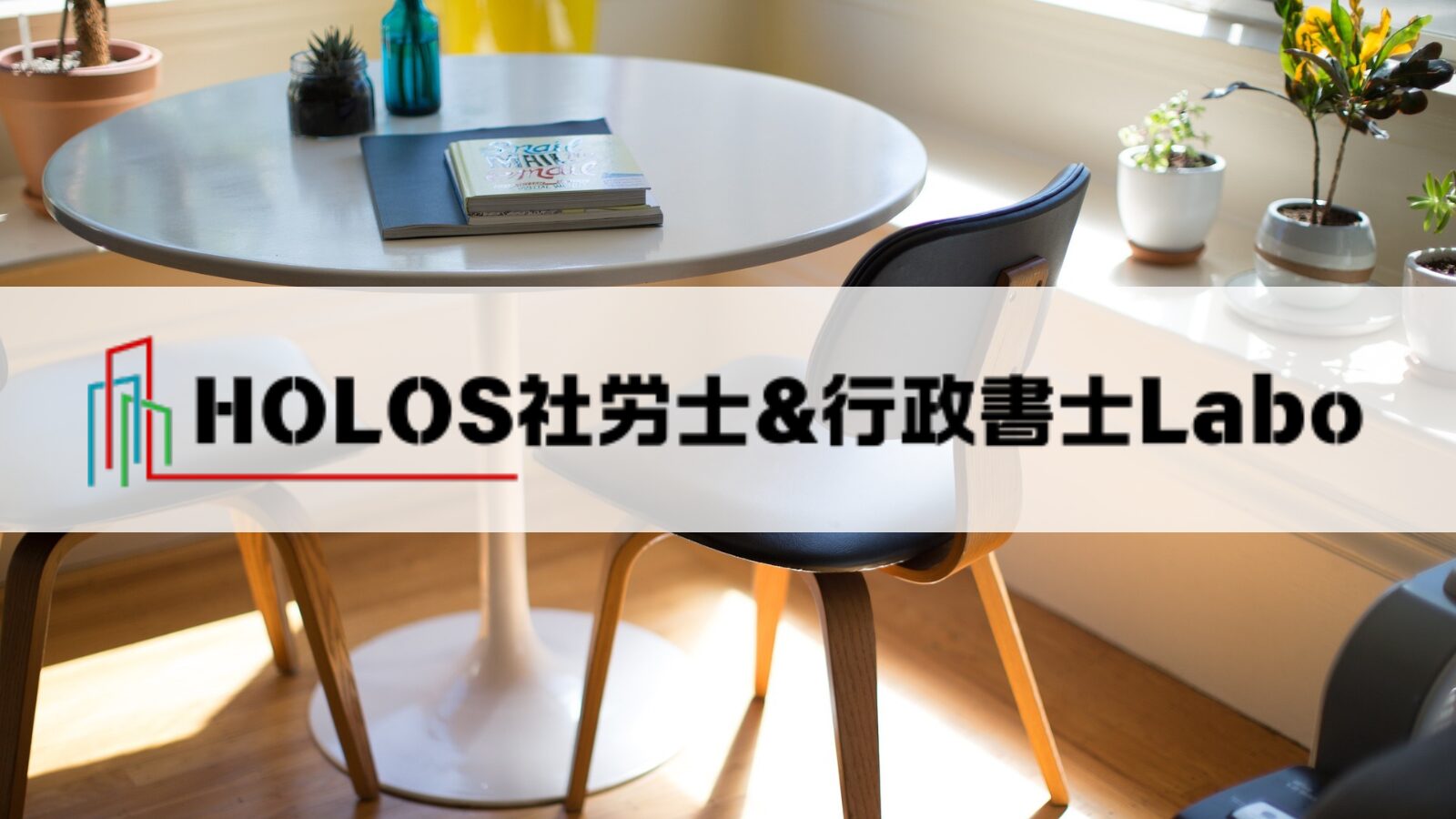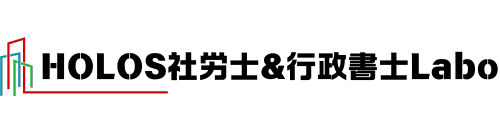【薬価80%引き下げ?】トランプ氏の大統領令と“薬の値段”の本当のコストとは
米国の医療政策を揺るがす発表がありました。
トランプ前大統領が「薬価を30~80%引き下げる」大統領令に署名すると宣言し、
薬価が急激に下がる可能性が示唆されています。
その背景には、米国民の高額な医薬品費用への強い不満と、政治的アピールの要素があると考えられます。
しかし、薬剤師として、この政策が本当に患者の利益に繋がるのか、少し慎重に見守る必要があると感じています。
急激な薬価引き下げがもたらす影響は、単に安価な薬を提供する以上に、現場に多大な副作用をもたらす可能性があるからです。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6538565
■薬価引き下げが起こした“日本の副作用”
日本において、薬価引き下げ政策は過去10年間で急速に進められてきました。
後発薬の推進や薬価改定が主軸となったその政策の結果として、以下の問題が顕在化しました:
- 供給不安の深刻化
- 医薬品の製造中止や供給調整が頻発し、薬が手に入らないケースが増加。
- 品質管理の後れ
- 後発医薬品の製造において、品質管理体制が追いつかず、薬の安全性に疑問符がつくことに。
- 現場の疲弊と経営圧迫
- 医療機関や薬局は薬価の低下と調剤報酬の抑制により経営が困難に。結果として、薬剤師の負担が増し、離職率が上昇。
安価で手に入りやすい薬が必ずしも最適な選択であるとは限りません。
品質と供給の安定性を犠牲にするような引き下げが、結局は患者にとって大きなコストとなることを、私たちは現場で目の当たりにしてきました。
■「最恵国待遇」は本当に最善か?
トランプ氏の提案する「最恵国待遇」は、米国が他国で最も安い薬価と同じ価格で薬を調達するというもの。
一見、薬価引き下げのためには理にかなった提案のように見えますが、このアプローチには深刻なリスクも含まれています。
急激な薬価の引き下げは、製薬業界におけるイノベーション投資の抑制や研究開発の停止を引き起こし、
さらには希少疾患向けの薬剤や治療法が供給されなくなる可能性も高いです。
さらに、急激な薬価調整がもたらす供給不安は、最も必要とされる治療薬が手に入らない状況を生む恐れもあります。
「安い薬が手に入らない」では本末転倒であり、安定した供給体制の維持が何よりも重要だと強調したいところです。
■薬剤師・社労士としての視点:薬価政策と現場運用の“ねじれ”がもたらす深刻な課題
薬剤師として私が強く感じるのは、薬価制度の改定と現場オペレーションの整合性のなさです。
特に日本では、後発医薬品の価格引き下げが制度的に先行しすぎた結果、製造インフラや品質管理体制の脆弱さが露呈しました。
供給停止・出荷調整が相次ぎ、「あるはずの薬が届かない」状況が常態化しています。
本来、薬剤師は患者に最適な選択肢を提示する立場ですが、薬が届かないことにより、
「在庫がある中から選ぶ」消極的な服薬提案を迫られる場面が増加しました。
これは、薬剤師の専門性の低下を招くだけでなく、患者の服薬アドヒアランスにも影響を及ぼすリスクがあります。
一方、社労士の立場では、薬価引き下げが経営の収益構造に与える中長期的影響を重く見ています。
とくに診療報酬体系において薬価差益の縮小が進む中、医療機関・薬局経営は次第に“固定費圧迫型”にシフト。
その中で導入された医療機関のベースアップ評価料や介護施設の処遇改善加算は、制度上存在しても、現場に十分浸透しないケースが少なくありません。
これらの制度は「財源確保済み」とされながらも、
実際の運用では、「算定の要件を満たすための労務管理の煩雑さ」「一時的な財政措置にすぎないことへの不安」「恒常的な賃金設計には使えない」といった、
運用面での課題が山積しています。
つまり、「制度はあるが使いにくい」「制度はあるが採用できず賃金に直結しない」という現場の“ねじれ”が、人材流出や士気低下を招いているのが実態です。
この構造的な課題を見逃したまま、「薬価だけを下げる」施策が進行すれば、
制度的インセンティブすら現場に届かなくなるという、制度疲労の悪循環に陥りかねません。
■まとめ:「薬価引き下げ」の本当の意味を考える
薬価引き下げは、短期的には患者にとってのメリットに見えるかもしれませんが、
その影響が長期的にどのように現場や患者に返ってくるかを、慎重に考える必要があります。
安価で手に入る薬の背後で起こりうる供給不安や、医療現場での負担増は、患者にとっても、医療従事者にとっても大きな問題です。
HOLOS(ホロス)社労士&行政書士Laboでは、医療・薬局・介護の現場支援を行い、
制度改革に伴う現場の影響やリスク管理に対するアドバイスを行っています。
▶ ご相談・お問い合わせ:https://holos-labo.com/contact/
投稿者プロフィール