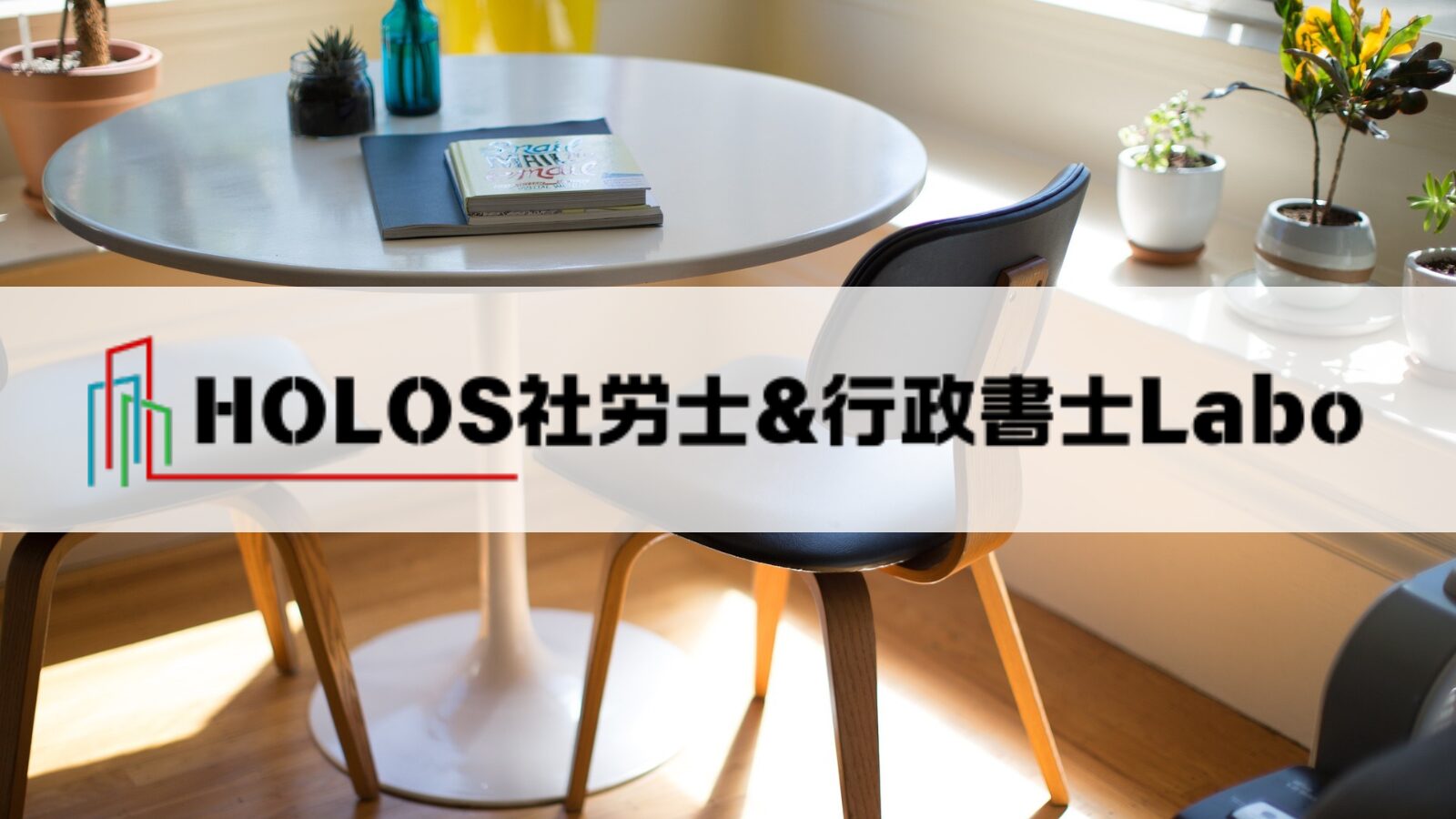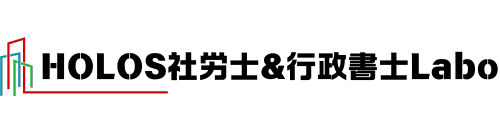アメリカの新薬価格、4年で2倍超──「高額薬」の波は日本にも影響する?
近年、アメリカで新たに承認・発売された医薬品の価格が急上昇しているというニュースが、ロイターの報道を通じて話題となっています。
2024年に発売された新薬の年間定価の**中央値は37万ドル(日本円で約5500万円)**に達し、わずか4年前(2021年)の18万ドルから2倍以上に。背景には、希少疾病(オーファンドラッグ)向けの医薬品開発が進んでいることがあります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d098c7612db5fe6adf2c37302b609ae2782793fa
■ 希少疾病向け新薬が全体の7割以上に
ロイターの調査によると、2024年に米国で発売された新薬のうち、7割以上が希少疾病向け。しかも、その4割強ががん治療薬でした。
こうした薬は対象患者が非常に少ないため、研究開発費の回収が難しく、1人あたりの薬価が高額になりやすいという事情があります。
■ 薬剤師として感じる現場への影響
薬剤師の立場から見ると、こうした高額薬の登場には複雑な思いがあります。
確かに、難病やがんなどの治療に希望をもたらす新薬は非常に価値が高いものです。一方で、そのコストを誰がどのように負担するのかは、医療制度全体に大きな影響を与えます。
たとえば、日本でも高額薬の増加は、保険財政や診療報酬制度に直結します。特に、薬局・病院・クリニックなどで**「選定療養」や「保険外併用療養費制度」**などが関係する場面も増えてくるでしょう。
■ 社労士の視点:雇用と医療費のバランス
医療費の増大は、保険料の引き上げや企業負担の増加にもつながり、労務管理にも影響します。
その点で、「ベースアップ評価料」や「処遇改善加算」など、人件費や処遇改善の仕組みと、高額な医療費の関係性をどうバランスさせるかは、経営や労務戦略としても非常に重要なテーマです。
たとえば、仙台・宮城県の中小病院や薬局などでも、処遇改善と保険収入の狭間で悩むケースは少なくありません。
■ 医薬品の価値をどう評価するか?
業界団体(PhRMA)や製薬企業は、「入院日数の減少」や「治癒の可能性」など、長期的には医療費を削減する効果があると主張しています。
確かに、遺伝子治療や分子標的治療薬の中には、“根治”に近づけるような革新的な治療も存在します。ですがその価格が、医療現場や制度にどう波及するのか、私たち一人ひとりが向き合う課題でもあります。
■ おわりに:医療現場に届く「制度の波」
高額薬の話は「アメリカのこと」と思いがちですが、日本でも薬価制度の見直しや後発医薬品政策などに影響が出る可能性があります。
薬局や病院、介護現場で働く皆さま、そして経営に携わる方々が、こうした国際的な動向にアンテナを張ることはとても大切です。
💡医療・薬局・介護の現場に寄り添う制度理解と実務支援を
制度改正や高額薬の影響をふまえた職場づくり、処遇改善、ベースアップ評価料への対応など、今後の医療・福祉経営のご相談もお任せください。
仙台・宮城県で活動する有資格者チームが、現場目線でわかりやすくサポートいたします。
投稿者プロフィール