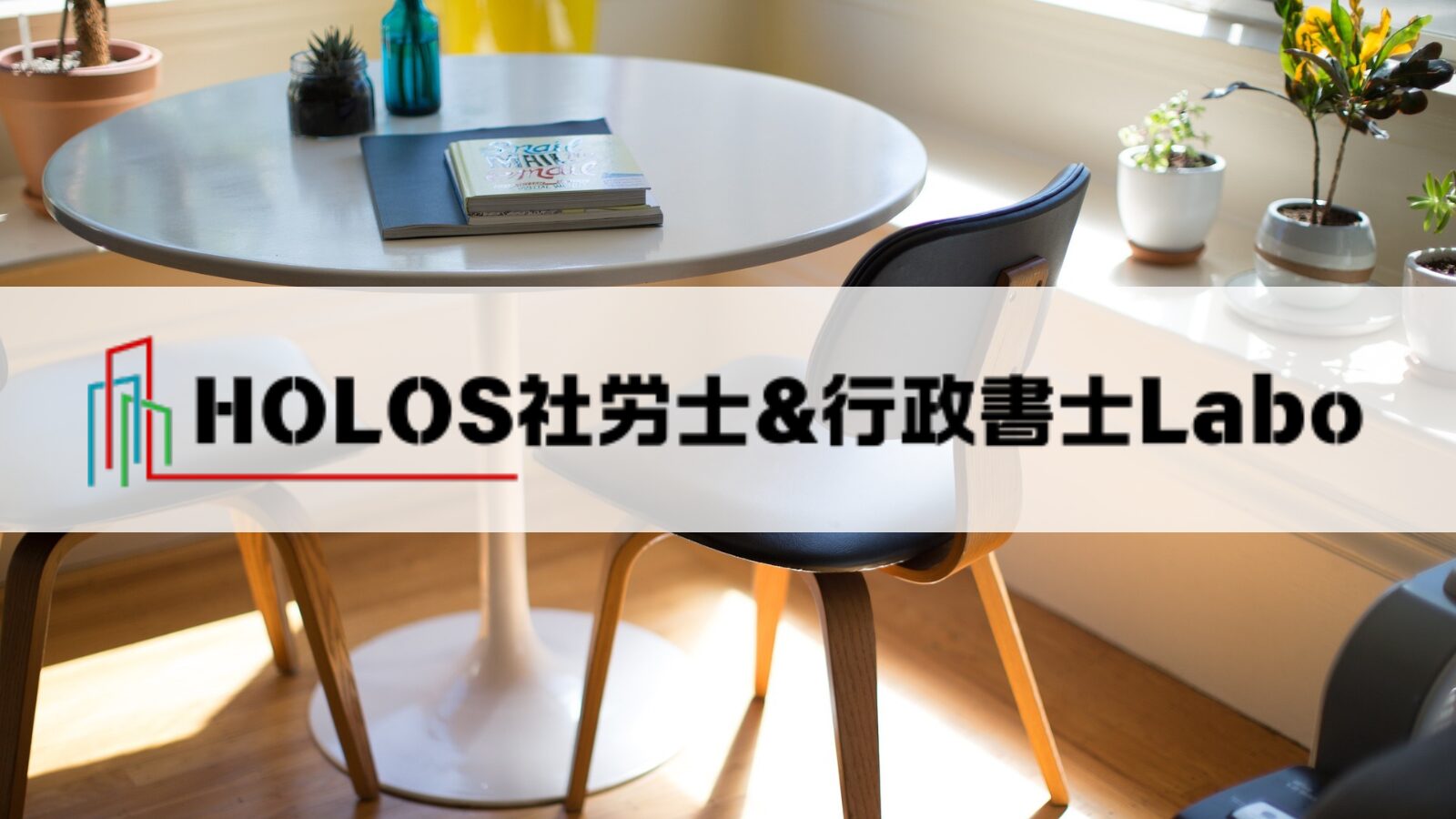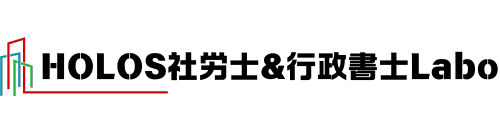ベースアップ評価料、「それだけ勉強しても対応できない」理由
最近もまた、ベースアップ評価料について「社労士に相談したが判断を誤られた」という医療機関のご相談がありました。
毎年のように制度改定がある中で、特にこのベースアップ評価料については、現場での誤解がとても多いと感じています。
「ベースアップ評価料だけ」学んでも対応は難しい
これは何度もお伝えしていますが、ベースアップ評価料は「単独の制度」ではありません。
診療報酬の一部として設計されている制度であり、その構造を理解しないまま「加算の要件だけ」追いかけても、実際の現場で制度を適切に運用するのはかなり困難です。
特に注意が必要なのは、「申請が通ればOK」ではなく、
その後の運用管理や要件維持、監査対応まで視野に入れる必要があるという点です。
そして場合によっては介護報酬との関係性も出てきます。
制度を点ではなく「線で」理解することが、非常に重要です。
職場環境等要件(職場改善加算)も同様です
実は、**職場環境等要件(いわゆる職場改善加算)**にも、同じようなことが言えます。
たとえば「掲示をすればいい」「チェックリストを埋めれば大丈夫」という表面的な対応では、
現場の実態や整合性を欠いた運用になってしまうことがあります。
職場改善加算は、形式的に整えることもできますが、
制度の目的や他の加算との関係性を理解していないと、申請後に指摘や修正が入るリスクもあります。
こちらもまた「書類作成」だけでは済まない、奥の深い制度です。
医療機関を支援する社労士として大切な視点
医療機関のベースアップ評価料も職場改善加算も、
単なる加算対応ではなく、職場の人件費や体制整備の問題そのものと結びついています。
正直に言えば、こういった制度に関して自信がない場合、対応を無理に引き受けることは、結果的に医療機関側の不利益につながるおそれがあります。
当事務所ではこう対応しています
当事務所では、医療機関の診療報酬制度の構造や運営実態をふまえて、
「制度をどう読むか」からご一緒に整理するという姿勢で対応しています。
私自身、薬剤師としての医療現場経験を活かしながら、必要に応じて他の医療専門職とも連携し、制度の本質を見失わないサポートを心がけています。
制度の「表面」だけでなく「裏側」も
ベースアップ評価料も職場改善加算も、現場で働く職員の処遇や環境改善につながる重要な制度です。
だからこそ、制度の表面だけでなく、その背景や運用のポイントも理解した上でサポートすることが必要不可欠です。
「申請はできたけど、実は間違っていた」「後から修正が必要になった」
そんなケースをこれ以上増やさないためにも、専門的な視点からしっかりとサポートできる体制を整えていきたいと考えています。
仙台・宮城の医療機関で、ベースアップ評価料や職場改善加算について不安や疑問がある方は、一度ご相談ください。
見落としがちな制度の“読み方”からご一緒に整理いたします。
HOLOS社労士&行政書士Labo
投稿者プロフィール