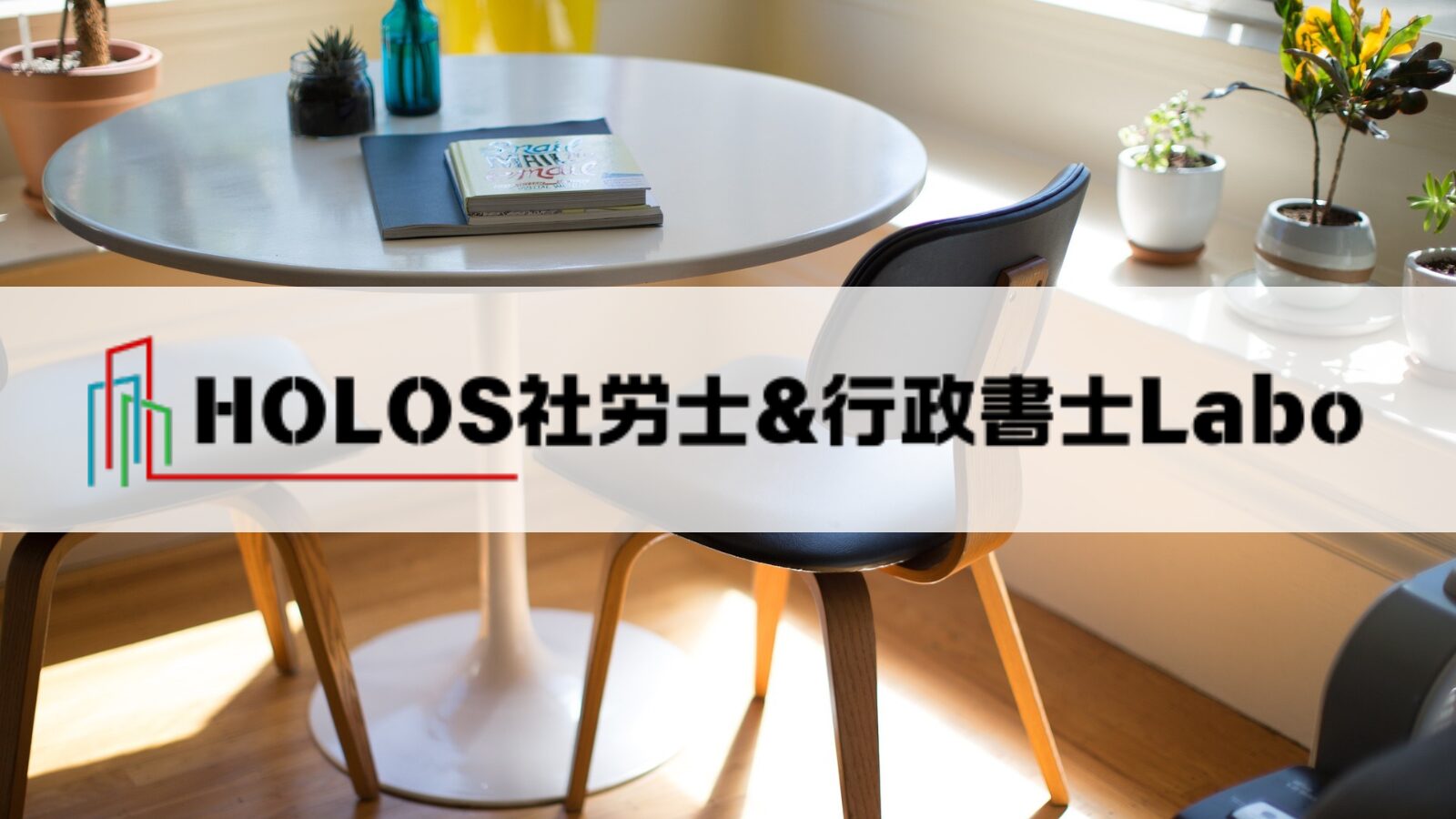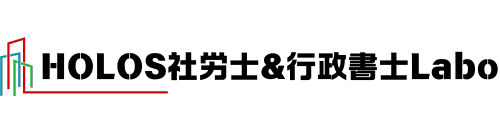緊急避妊薬が市販薬に? 〜薬剤師・社労士の視点から制度の意義と課題を考える〜
2024年6月、あすか製薬が「ノルレボ錠」(緊急避妊薬)を処方箋なしでも購入可能な「特定要指導医薬品」として申請したことが明らかになりました。これは、改正医薬品医療機器等法(薬機法)の成立を受けての動きです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/49812bc8b852fded2f4a54854a7e08f85d862aec
■特定要指導医薬品とは?
一般的に「市販薬」と聞くと、誰でも簡単に購入できるイメージがありますが、「特定要指導医薬品」はその中でも特に慎重な取り扱いが求められる医薬品です。
具体的には:
- 薬剤師が対面で情報提供(説明)を行った上で販売
- インターネット販売は禁止
- 販売後も使用状況の情報収集が必要
つまり、**「販売が許可されている市販薬ではあるが、ネット販売などはできず、薬剤師による管理が前提」**という特殊な位置づけです。
■なぜ今、市販化が進められているのか?
背景には、避妊の失敗や性暴力などによる望まない妊娠の防止という切実な課題があります。性交後72時間以内の服用が必要な緊急避妊薬が、すぐに手に入らない現状に対して、多くの当事者や専門団体が改善を求めてきました。
2023年11月からは、16歳以上の女性を対象とした試験販売が全国約330店舗の薬局で始まっています。今回の申請により、販売薬局数の拡大が期待されます。
■薬剤師としての視点:情報提供のバランスがカギ
緊急避妊薬は、誤解や偏見も多く、また正しい使用法の理解も不可欠です。薬剤師の立場から言えば、対面販売による確実な説明と理解の共有は極めて重要です。
一方で、薬局によっては営業時間の制限やプライバシー面の課題も残されており、「すぐに必要な時に手に入らない」という本来の目的を達成できない可能性もあります。
■社労士としての視点:働く女性の健康課題と医療アクセス
今回のような緊急避妊薬の市販化に向けた動きは、医療機関にすぐにアクセスできない状況にある方や、性暴力など切迫した事情を抱える方への対応策のひとつとして、制度的な整備が進められているものです。
社労士としても、女性の健康や安全に関わる制度や動向には注視しておく必要がありますが、今回の市販化の趣旨は、あくまで緊急避妊という医療上の必要性への対応である点を見誤らないことが大切です。
■個人的な所感:将来的には調剤報酬上での評価を
薬剤師としては、今後こうした医薬品の緊急かつ適正使用に対する現場負担支援に関しても、調剤報酬制度で評価される仕組み(例:調剤版ベースアップ評価料の新設)を期待しています。すでに介護・医療の現場では、処遇改善加算やベースアップ評価料が定着しつつありますが、薬局で働く薬剤師の役割にも光が当たる制度設計が必要ではないでしょうか。
■仙台・宮城の医療機関・薬局・介護事業者の皆様へ
制度が変わる時には、現場での対応が追いつかず、トラブルになるケースもあります。
HOLOS(ホロス)社労士&行政書士Laboでは、薬剤師・社労士の資格を持つ代表が、制度の本質や実務上のポイントをわかりやすくご説明しています。
「医療・薬局・介護といえばホロス」と言われるよう、今後も支援を続けてまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール