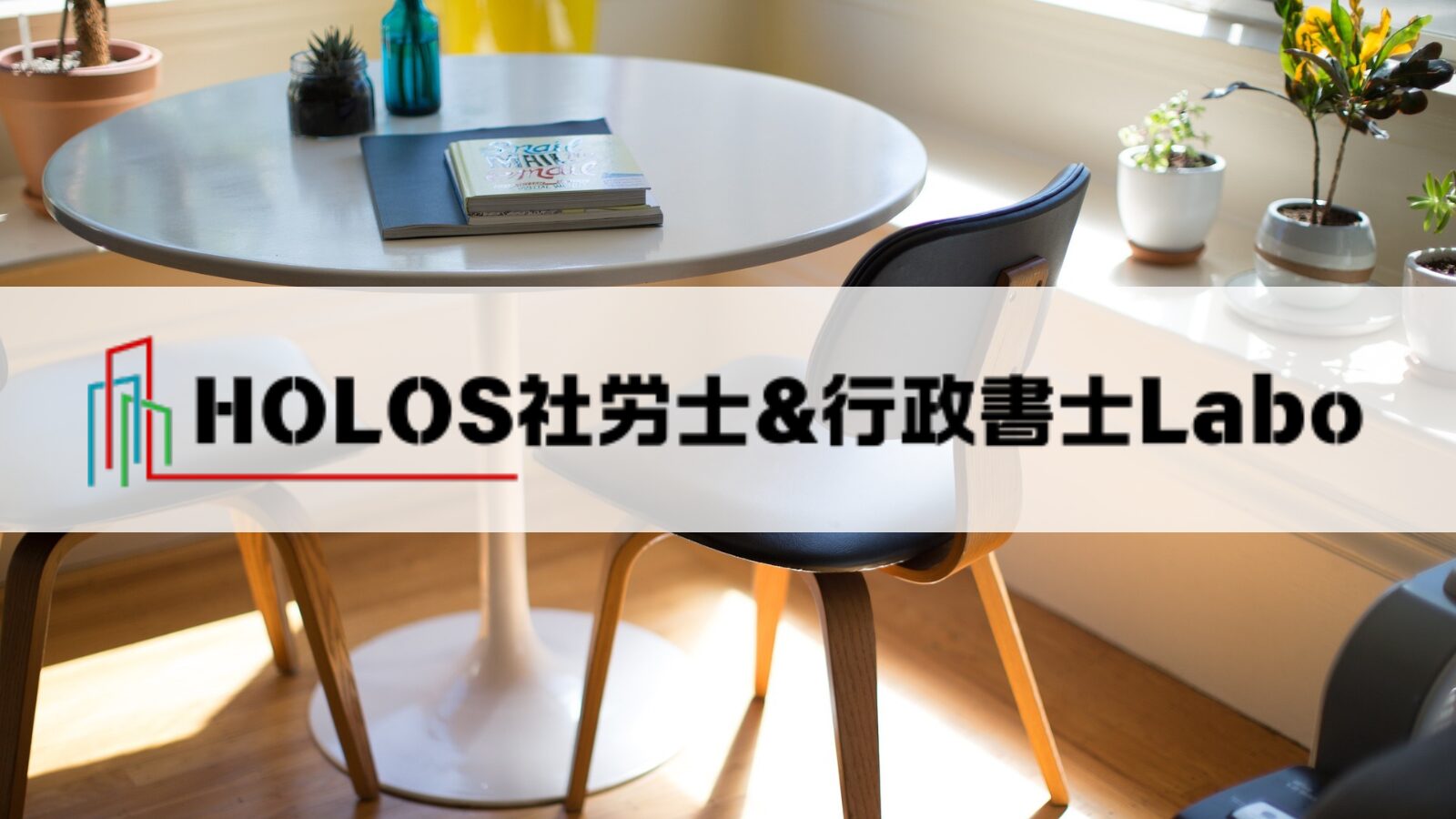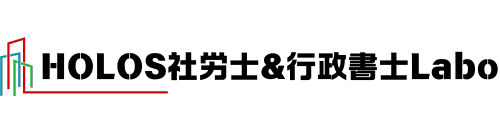阪大病院で抗がん剤の過剰投与ミスが発覚:システム不具合が原因
阪大病院で抗がん剤の過剰投与ミスが発覚:システム不具合が原因
2024年8月21日
大阪大学医学部附属病院で、薬の投与量を計算するシステムに不具合が発生し、60代の男性入院患者2人に抗がん剤を過剰に投与していたことが明らかになりました。このうち1人は、抗がん剤による神経障害が起こり、歩行が困難になる事態に。病院とシステムを開発したメーカーは、患者や家族に謝罪し、再発防止策を徹底すると発表しています。
過剰投与の詳細
- 投与期間: 2024年1月から2月にかけて
- 対象患者: 60代の男性患者2名
- 投与量:
- 1人目: 通常の約2倍の抗がん剤を3日間投与。その後、歩行困難となる神経障害が発生。6月にがんの進行により亡くなったとされています。
- 2人目: 通常の1.2倍の抗がん剤を1回投与。現在までに明らかな影響は確認されていません。
システム不具合の原因
原因は、薬の投与量を計算するシステムに不具合があり、誤った投与量が表示されたことにあります。このシステムは大阪のメーカーが開発したもので、同様の問題が他の35の病院でも使用されていますが、現時点では同様の問題は報告されていません。
コメント: 薬剤師・社労士として
今回の過剰投与問題は、システム依存が強まる医療現場におけるリスクの一つが露呈した事例です。薬剤師の視点から見ても、システムに頼りすぎることは危険であり、必ず人的確認が必要です。特に抗がん剤のような高リスクの薬剤は、少しの投与量のズレが患者の生命に大きな影響を与えるため、慎重な対応が求められます。薬剤師と医師が連携し、システムを利用した結果にも常に疑問を持ち、二重チェックを徹底することが不可欠です。
社労士の視点では、再発防止策として病院全体での組織的な対応が必要です。システムの不具合が原因とはいえ、投与ミスを防ぐための安全策がどの程度整備されていたかが問われます。職場内でのヒューマンエラーを防ぐために、適切な研修や教育の実施が不可欠ですし、組織としての責任体制も明確にすべきです。
医療の安全性を高めるためには、技術に依存するだけでなく、職員一人ひとりが自らの役割をしっかり果たし、ミスを防ぐ努力を継続していくことが重要でなのですね。
宮城県・仙台市の社労士・行政書士 HOLOS社労士&行政書士Laboでは今後もお役に立てる情報や「豆知識」を投稿してまいります。
薬剤師・社会保険労務士・行政書士
石田宗貴
投稿者プロフィール