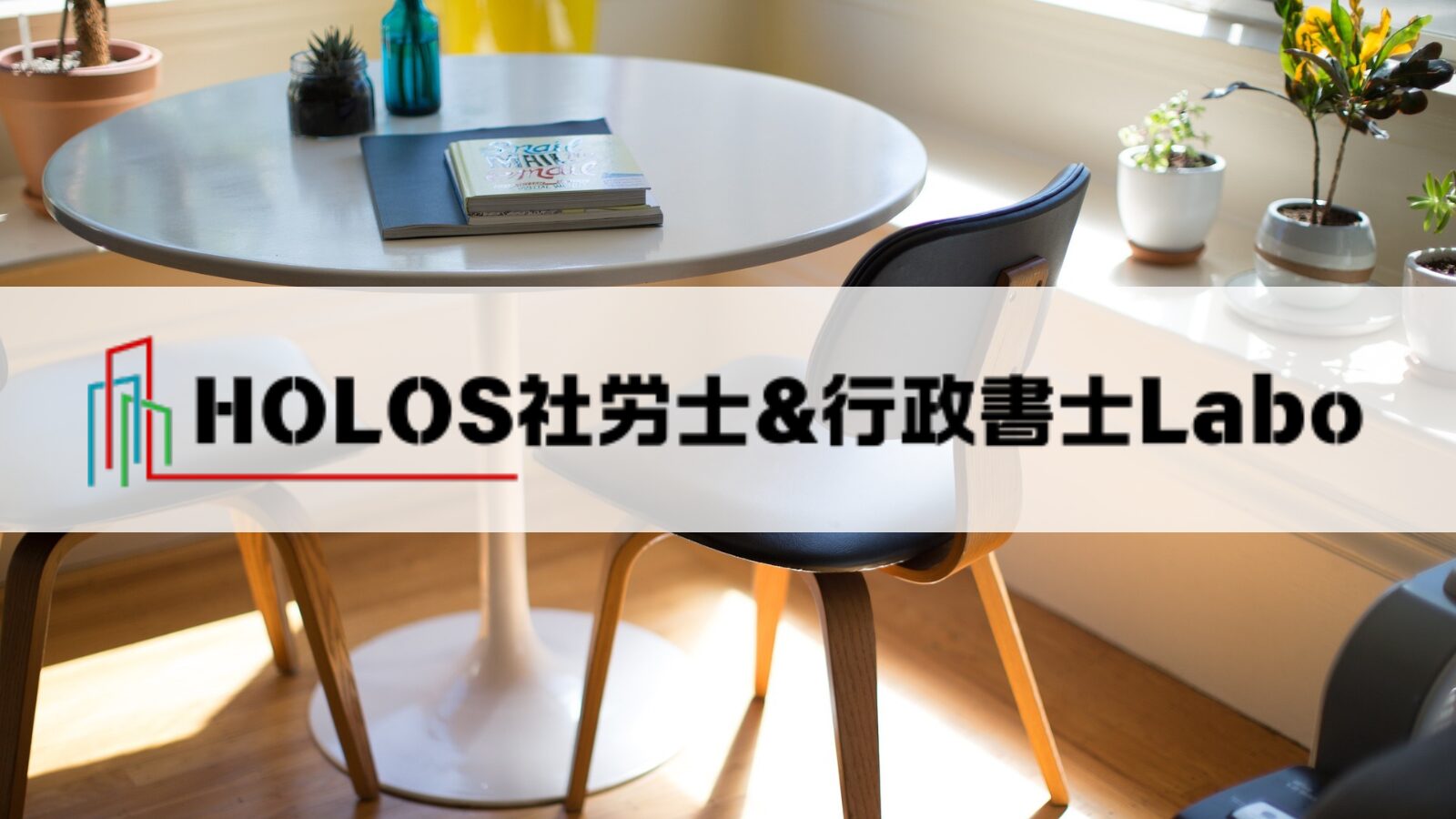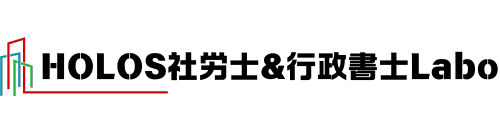電子処方箋と電子カルテ、2030年に向けて──医療DXが描く未来と職場への影響
こんにちは。医療・薬局・介護の現場と制度の橋渡しに取り組んでいる立場から、今回は厚生労働省が新たに発表した「電子処方箋」と「電子カルテ」導入目標についてご紹介します。
電子処方箋・電子カルテとは?
マイナ保険証の活用を軸に、医療データを医療機関・薬局間でリアルタイムに共有する仕組みが、「電子処方箋」や「電子カルテ情報共有サービス」です。
これにより:
- 重複処方や飲み合わせのリスクを回避
- 複数医療機関の受診履歴が一目でわかる
- 災害時の診療継続にも対応可能
といった利点が期待されています。
新たな国家目標は「2030年、全国展開」
厚生労働省はこれまで、2024年度中に全国導入を目指していましたが、2025年6月時点で医療機関の導入率はわずか約1割。
この現状を受け、導入目標を「2030年までにおおむねすべての医療機関へ」と見直しました。
その背景には:
- システム改修費や運用コストの負担
- 現場スタッフのIT習熟度の差
- 他システム(レセコン等)との連携課題
といった「見えづらい導入障壁」があります。
専門職の実感:「効率化」ではなく「質の向上」
薬剤師や労務支援に携わる立場から見ると、この電子化は“業務効率”以上の意味を持ちます。
- 患者にとっては、自分の情報が一貫して伝わることで、治療の安心感が増す
- 医師・薬剤師・看護師・ケアマネジャー等が、共通の情報基盤を持てることで、チーム医療が本来の力を発揮できる
つまり、「人を支える仕組み」の改革なのです。
制度を“導入できる職場環境”に整えるには
電子カルテや処方箋の導入は、直接的にベースアップ評価料の算定要件ではありません。
しかし、業務改善やIT活用、スタッフ教育体制の整備といった取り組みは、間接的に処遇改善や人材定着の基盤となる重要な要素です。
DXの導入が、結果として「働きやすい職場づくり」「継続的な賃上げ体制」に繋がる流れをつくっていくことが、今後の医療機関の“強み”になります。
HOLOSが支援できること
HOLOS(ホロス)社労士&行政書士Laboでは、電子処方箋・電子カルテ導入に際しての以下の支援を行っています:
- 業務フローと人員配置の見直し支援
- システム導入に伴う労務管理の調整
- 教育・研修の設計と実施
- 関連助成金・補助金の活用支援
ただITを導入するのではなく、「それが現場で使える」状態をつくること。それが本当の制度活用です。
制度が変わるとき、現場はいつも戸惑います。
でも、それを「新しい仕組みをつくるチャンス」に変えていけるよう、私たちも伴走したいと思います。
投稿者プロフィール