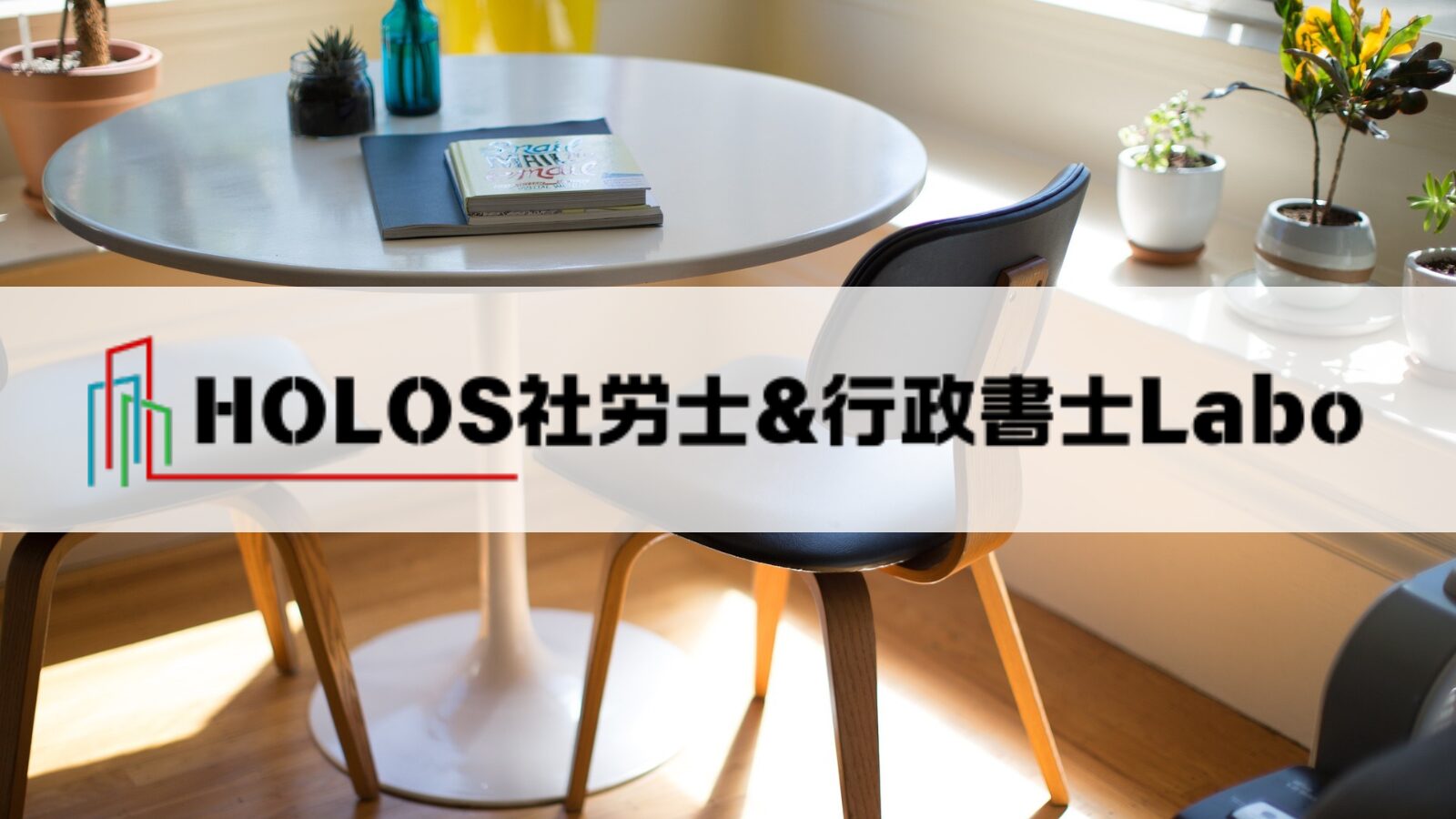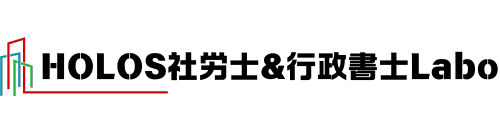無痛分娩 約120人に1人で合併症 ~安心・安全な出産のために知っておきたいこと~
2025年5月、日本産婦人科医会が発表した調査結果によると、「無痛分娩(麻酔によって陣痛を緩和する分娩方法)」において、約120人に1人の割合で出血などの合併症が起きていることがわかりました。
出産における選択肢が広がる一方で、安全性やリスクについても改めて考える必要があることが示された形です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250518/k10014808541000.html
■調査の概要:全国で5万件超の無痛分娩を分析
調査は、全国の1900あまりの産科医療機関を対象に実施され、2023年に417施設で行われた無痛分娩5万3000件超について分析されました。
そのうち、以下のような合併症が報告されています。
- 母体の合併症(出血や子宮損傷など):454件(約120人に1人)
- 麻酔に関する合併症(麻酔が全身に影響するなど):38件
- 新生児の合併症(出血など):21件
これらの数値からも、基本的には安全に行われているものの、通常の分娩より医療的介入が多いぶんリスクもゼロではないという現実が見えてきます。
■薬剤師としての視点:医療の介入が増える分、準備も大切
薬剤師の立場から見ても、無痛分娩に使用される麻酔薬の適正使用や投与管理は極めて重要です。特に妊産婦さんは体の状態が変化しやすく、通常とは異なる反応が出ることもあります。
出産は命を守る医療行為でもあります。無痛分娩を選ぶ際は、「痛みの軽減」というメリットだけでなく、「どんな準備や説明が必要か」「どんな副作用の可能性があるか」など、医師・助産師・薬剤師など多職種とのコミュニケーションが大切です。
■社労士としての視点:産前産後の就労支援と制度整備
無痛分娩を希望される背景には、「出産後もスムーズに復職したい」「育児と仕事を両立したい」という前向きな想いがある方も多くいらっしゃいます。
こうした想いに応えるためにも、企業や医療機関における「出産後の職場復帰支援」や「体調に配慮した働き方」などの制度整備は非常に重要です。
制度が整えば整うほど、無痛分娩や働き方の「選択肢」を安心して取れるようになります。
■「選択肢を支える制度づくり」も、HOLOSの支援領域です
仙台・宮城県をはじめ、東北エリアの病院・クリニック・薬局・介護事業所の皆さまからも、
「出産や育児にまつわる制度をどう設計すればよいか」
「スタッフの健康支援や休職・復職制度を見直したい」
といったご相談を多くいただきます。
HOLOS(ホロス)社労士&行政書士Laboでは、医療・薬局・介護に特化した社労士・薬剤師の視点で、現場に合った制度づくりをサポートしています。
■まとめ:情報と制度、どちらも大事に
無痛分娩は、痛みの少ない出産方法として多くの方に支持されていますが、今回の調査のように一定のリスクがあることも理解したうえで選択することが大切です。
また、無痛分娩の背景にある「安心して産み、働ける社会づくり」には、職場や医療機関での制度設計も欠かせません。
出産という人生の大きな節目に、医療と労務の両面からサポートできるパートナーとして、これからもHOLOSが皆さまのお力になれればと思います。
投稿者プロフィール