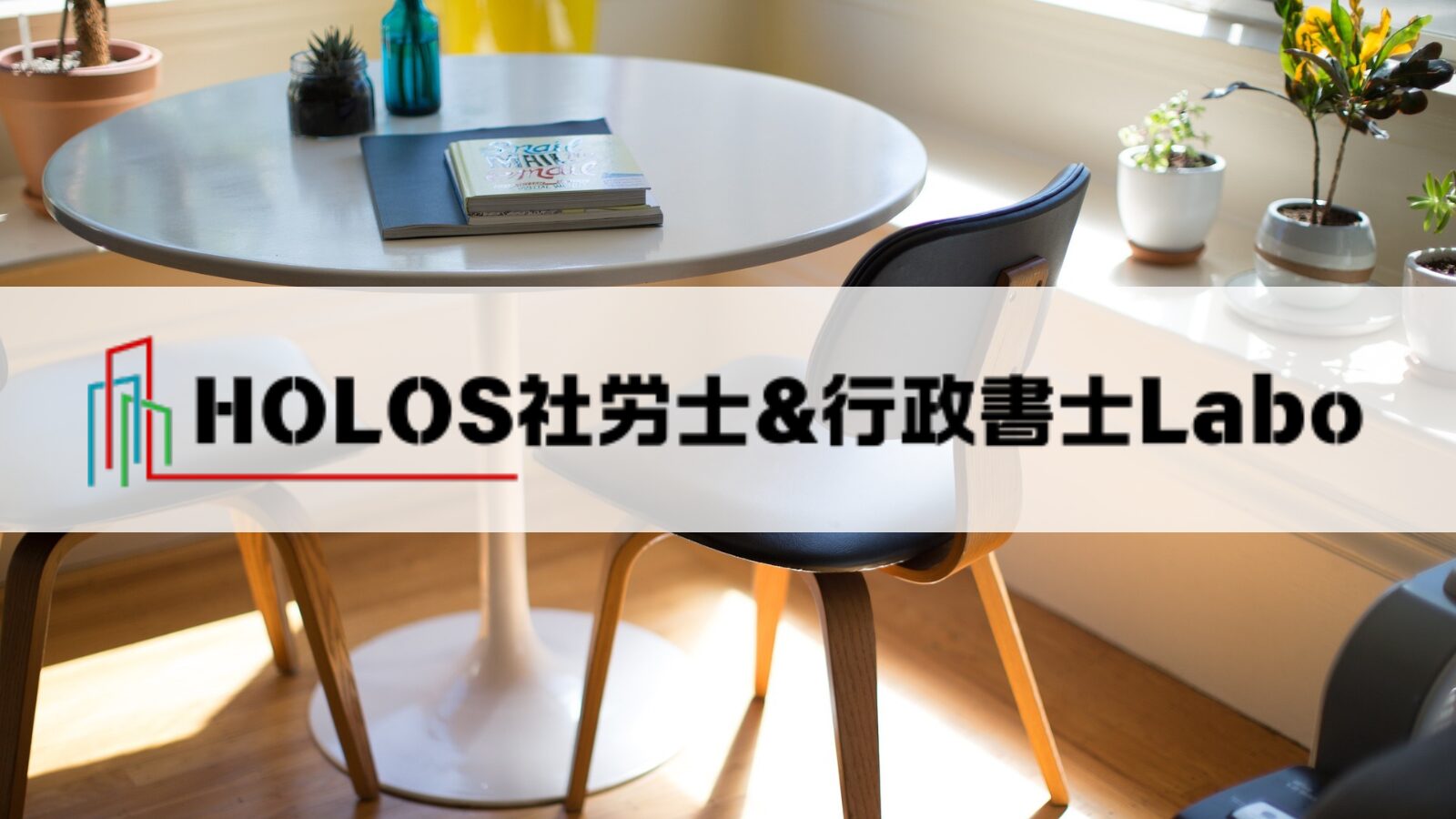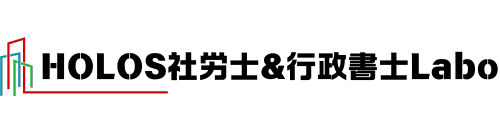食中毒、営業停止中の弁当販売──現場と制度、どこに課題があるのか
こんにちは。医療・介護・薬局に関わる現場を、制度と労務の面から日々サポートしている立場から、今回報道された「営業停止処分中の弁当販売と再発した食中毒事件」について、少し掘り下げてみたいと思います。
大阪・河内長野市の日本料理店が、営業停止中にもかかわらず仕出し弁当を販売し、その後、複数の利用者からノロウイルスが検出されたというニュース。
過去にはミシュラン掲載歴もある店で、さらに3月には再度食中毒を起こしていたことも明らかになっています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250616/k10014836431000.html
“知識はあっても防げない”現場のリアル
医療機関・薬局・介護施設でも同じことが言えますが、ノロウイルスのような感染症対策は「知識だけでどうにかなる」ものではありません。
私自身、薬剤師として現場にいた経験から、衛生管理の手順や嘔吐物処理のマニュアルがあっても、忙しさや人手不足から徹底できない場面を何度も目にしてきました。
また、社労士として感じるのは、衛生管理や感染対策は「個人の意識」に任せてしまうと継続が難しいという点です。
どれだけ真面目なスタッフでも、制度や仕組みが整っていなければ、いつか必ずほころびが出ます。
繰り返さないための“仕組み化”
今回の事件の背景には、「営業停止中は売上がなくなる」「予約を断りにくい」といった経営的なプレッシャーもあったのかもしれません。
しかし、衛生管理に例外をつくれば、必ず現場は迷います。
たとえば、医療や介護施設では、「感染症発生時の対応マニュアル」を定期的に見直したり、「衛生教育の実施状況」を人事評価に組み込むなど、制度面での支えをつくっていくことが再発防止につながります。
このとき、「処遇改善加算」や「ベースアップ評価料」の活用は非常に効果的です。
単なる給与アップの手段ではなく、「衛生的で安全に働ける職場づくり」への投資としてとらえる視点が重要です。
HOLOSが支援する“見えるルールづくり”
HOLOS(ホロス)社労士&行政書士Laboでは、医療・薬局・介護の現場で、衛生管理や感染症対応を労務・制度の面から“仕組み化”するお手伝いをしています。
大事なのは、「忙しくても守れるルール」であること。
現場で無理なく続けられるマニュアル、教育体制、評価制度を整えることで、「なんとなく大丈夫だった」という感覚から、「だから大丈夫だと言える」体制へと変えていくことが可能です。
衛生意識を「人の努力」にだけ頼るのではなく、
制度と労務の力で、“安心して働ける”現場づくりを。
この事件をきっかけに、ぜひ一度、自施設のリスク管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール